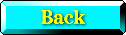|
思いもかけない担保要求
DDKは異業種の中小企業800社余を会員とする事業協同組合です。中核事業に金融事業があります。
毎年6月と12月に、会員向けに一社500万円以内、期間6か月の無担保融資を行うもので10数年の実績があります。
資金が広く中小企業に均霑する点で社会的意義のある制度です。
今年の盆資金73先 2億6070万円は前回(昨年年末)に準じ次のとおり借入申込みしました。
三和 3000万円(前回と同額)
A行 3000万円(前回と同額)
B行 2億70万円(前回2億830万円)
AB両行は、申込通り応諾してくれましたが三和銀行だけが、資金必要日当日になって、3000万円の定期預金担保を条件としてきました。
理由を糺しても、“総合的判断による。大きな流れのなかで、こうした結論になった。”の一点張りで、全く説明になっていません。
説明責任求め質問状提出
三和の結論は、要するに定期預金担保以外いっさい与信を行わない。信用貸ゼロというもので、既往取引実績、借入金の性質(多数転貸、短期)組合の財務内容から到底承服できるものではありません。
同行からの、同種資金の借入は、92年以降連続15回に及び、最高時は 1億2450万円、平均は4500万円です。これ以外の借入は定期預金担保による当座貸越枠1000万円のみです。もちろん延滞は取引開始以来一度もありません。
こうした問答無用の身勝手は、中小企業団体としても看過できません。
支店レベルでは埒があかないので6月14日頭取宛に下記主旨の質問状を提出しました。
質問1 昨年12月の年末資金借入時(無担保で3000万円借入)から今回までに信用上マイナス評価となる事情変更があったのか。あったとすれば教訓にしたいので具体的に示していただきたい。
質問2 事情変更はないが、見直しの結果、預金担保を必要と判断されたのであればその根拠を具体的に示していただきたい。
質問3 支店回答の「大きな流れ」の中身は、組合にとって死活的重大事なので、わかりやすく説明していただきたい。
|
質問に対し6月20日支店長経由で三和銀行としての「回答」がありました。それは、質問1、2、3とも“総合的判断としか言いようがない”という空疎且真摯さに欠けるものでした。
戦略的貸し渋りに監視の目を
質問1と2は、説明責任を別とすれば、いわば個別の借手の受信能力の話です。しかし質問3は次元が違います。大銀行の戦略にかかわる問題です。個別事案にとどまらない、中小企業団体としても強い関心をもつべき問題だと直感しました。
一時期、自己資本比率や資金繰りからくる「貸せない貸し渋り」がありました。現段階での大銀行の貸し渋りは、統合・合併による再編成の流れのなかでの、戦略としての貸し渋り、「貸さない貸し渋り」です。
経済再生のためにも、金融アセスメント法の成立が急がれるところです。
協同金融の裾野をひろげよう
DDKの金融を、私たちは小口・協同金融と呼んでいます。特徴は、協同の理念に基づく仲間うちの、顔の見える金融です。
年末・盆資金のような複数転貸は、銀行としては、組合のもっている審査能力(情報、事業運営体制、事故対応力)を活用することにより省力化とリスク軽減が図れるという利点があります。会員からは、通常 銀行から借りにくい資金が、比較的容易に借りられると喜ばれています。
バック・ファイナンスのメインは組織金融を標榜する商工中金が担ってくれます。
事業の成否は、事務局体制とりわけ、人を得ることと 貸倒れに備えての防衛積立金制度にあります。
DDKでは、融資額の5%の連帯防衛積立金を預かっています。この制度は、相互扶助の精神にもとづくリスク分担システムで、一種のグループ共済です。
この制度が リスクテイク能力 ひいては受信能力の鍵となっています。
事業協同組合が、志をもって転貸融資をひろげ、銀行が、資金面でバックアップすれば、商工ローンの被害も減少するのではないでしょうか。現役の銀行労働者やOBたちが、この分野で貢献されることを願ってやみません。
(銀行労働調査時報2000年7・8月号(607号)掲載)
| ![]()